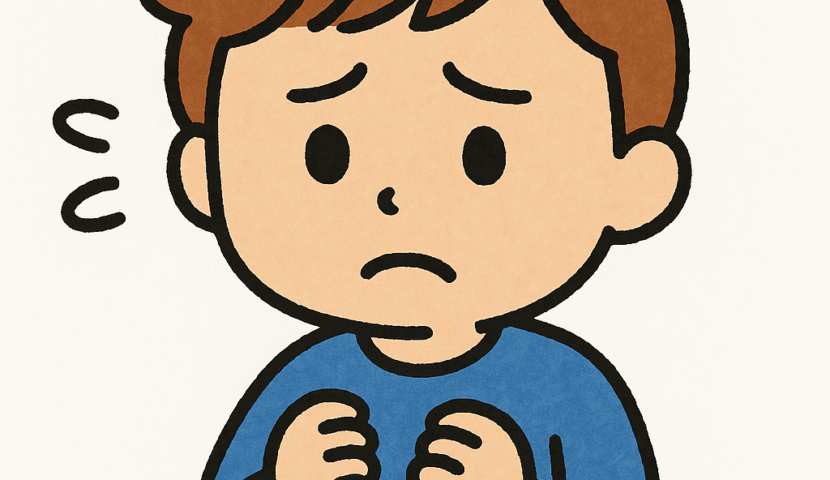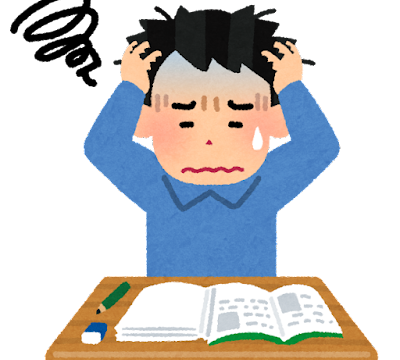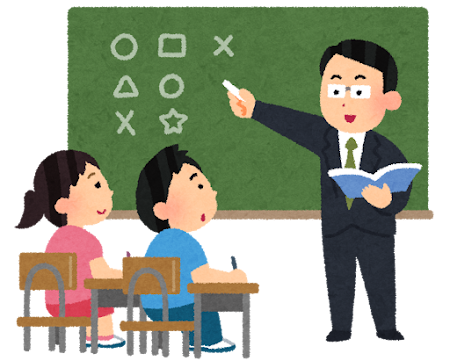以前購入して読了した本ですが、再度読んでいます。
不安の強い子どもを持つ保護者のみなさんにはぜひ知っておいてほしいことがたくさん載っています。
不安の強い子どもに、親(※この文章の中では簡単に「親」と書きますが、実の親でなくてもかまいません。子どもを養育している人全てを含みます)はどうしても巻き込まれてしまいます。
『巻き込まれは、子どもを助け、子どもとご家族が一日をなんとか乗り切るためにあなたが見つけたツールなのです』
巻き込まれることは、決して悪いことではないのです。
この本では子どもの不安に対処するうえで、約に立つ「巻き込まれ」と役に立たない「巻き込まれ」を分けています。
役に立つ巻き込まれはたとえば、子どもが不安の問題のために学校に行けなかったとき、親が付き添って学校に行かせることです。
これは徐々に前進するものであり、子どもの不安に対処する力が増すにつれてなくしていくことができます。
一方で役に立たない巻き込まれは、子どもがより多くのことを避けるようになったり、より対処することを減らすようになる場合です。
たとえば、子どもが多少の困難があっても一人で学校に通っているとしたら、一定の日に学校に同行するのは、役に立たない巻き込まれの可能性が高いでしょう。
(もちろん、例外もたくさんあります!)
『不安に対処できない、不安を引き起こす可能性のある状況を避けなければならないという子どもの信念を強化するような「巻き込まれ」は、役に立たないものです。』
さらにこの本には、役に立たない巻き込まれを減らしていくための方法が載っています。
まずは、どんな「巻き込まれ」をしてしまっているかをチェックします。
一日の中で、どんな時間にどんな「巻き込まれ」があるか、なるべく具体的にチェックしていきます。
まずは気づくことが大切です。
次は子どもに対する「支援」について考えます。
「支援」とは何でしょうか?
一見すると、周りの人を頼ったり、具体的な配慮などを考えるかもしれません。
この場合はそうではなく、親の心の持ちようです。
支援とは、「受容」と「自信」の2つです。
親がこの2つを持っていることがとても重要なのです。
『子どもの不安に対して、親が子どもが本当に不安であるのを理解していること、子どもが不安であることを責めないこと(受容)、子どもが本当に不安に対処できるとあなたが知っていること(自信)を、子どもに伝える形で対応すると、あなたは支援的になれます。』
支援的になるということは、子どもが突然不安を感じなくなることを意味しません。
たとえば保護者が何か受容的なことを言って、それで子どもが不安を感じないように期待するならば、それは本当の意味での受容ではないですよね?
もし保護者が、子どもが不安に対処できると信じていると行ったとしても、行動がそれを信じていないことを示していたら(たとえば、支援的な宣言のすぐあとに「巻き込まれ」をしてしまったら)、子どもは結局あなたが子どもに対し自信を持っているとは思わないでしょう。
変えていくのは、行動から変えていくことが一番です。
子どもにかける言葉を変えていきましょう。
次に、「巻き込まれ」を減らすことを考えます。
まず、一つの「巻き込まれ」を選びます。
それに対して、今行っている「巻き込まれ」をどのように変えるかを考えてみます。
たとえば、子どもが一人で部屋にいるのを怖がる場合、保護者がいつも一緒の部屋にいることになるかもしれません。
そうではなく、例えば、10分間は子どもと一緒の部屋にいるが、その後は保護者は別の部屋に行くようにするというようなことです。
このような計画を立てた後、子どもに計画について伝えます。
このときも、「なぜ」「何を」「いつ」「誰が」「どのように」「どのくらい」変更するのかが、メッセージの中に含まれていることを確認します。
その後は、実際に計画に取り組みます。
子どもが反発したり、パートナーと意見が合わなかったりするかもしれません。
それでも続けていくことに大きな意味があるでしょう。
子どもの不安で悩んでおられる保護者の方に、ぜひ読んでいただきたい本です。なかなか分厚くて、読むのが難しいかもしれませんが、できたらぜひ!
もし不安の強い子どもへの対応でお困りの方は、なぎさ心理相談室にご相談することもできます。
参考文献:『「巻き込まれ」に気づいて子どもを不安から解放しよう!』