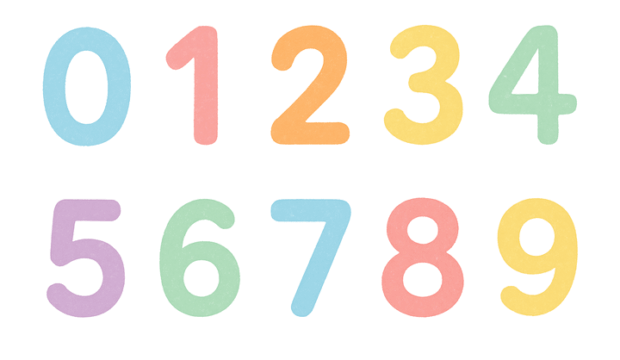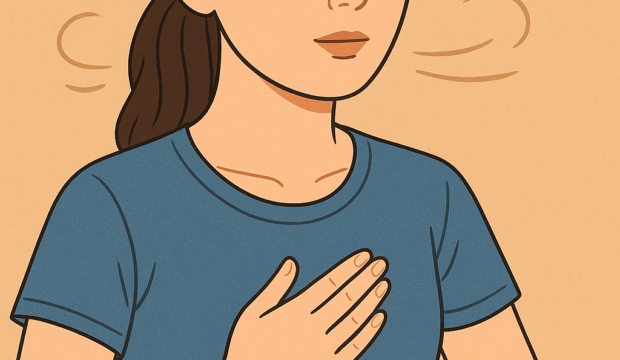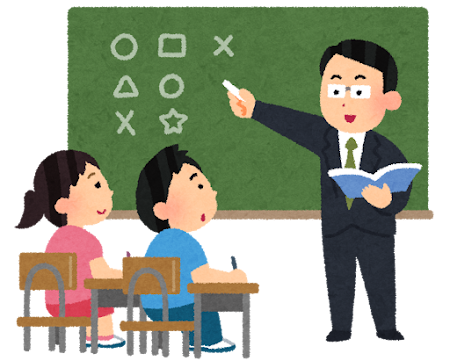心理学における「バウンダリー」(境界)とは、個人が他者との間で設ける心理的な「境界線」のことです。自己と他者を区別し、どこまでが自分の領域であり、どこからが他者の領域であるかを明確にするためのものです。バウンダリーを適切に保つことは、精神的な健康や健全な人間関係を維持する上で非常に重要です。
心理学的バウンダリーの役割
バウンダリーは、個人のアイデンティティ、自尊心、感情の安定を守るために必要です。適切なバウンダリーを設定できていると、以下のような効果が得られます。
自分の感情や行動をコントロールできる: 他者の影響を受けすぎることなく、自分の感情や行動に責任を持てるようになります。
他者からの過度な依存を防ぐ: 他人の要求や期待に過度に応えすぎることなく、自己を守ることができます。
精神的・感情的なバランスの維持: 他者の感情や問題に巻き込まれすぎず、自己の感情や心理状態を安定させることが可能です。
バウンダリーがうまく育たないとどうなるか
バウンダリーが曖昧だったり、適切に育っていないと、以下のような問題が発生することがあります。
- 他者にコントロールされやすくなる: 他人の要求に応えすぎてしまい、自分自身のニーズや希望を後回しにする傾向が強くなります。
- 過度なストレスや疲労感: 自分の限界を超えて他者に尽くすことで、精神的にも肉体的にも消耗してしまいます。
- 感情の境界が曖昧になる: 他人の感情や問題を自分のものとして抱え込んでしまい、感情的な混乱が生じることがあります。
- 依存的な関係: バウンダリーがしっかりと保たれていないと、他人との間に依存的な関係が生まれやすくなり、お互いに健康的な距離を保てなくなることがあります。
「バウンダリーのない家庭」とは、家庭内で個人のプライバシーや感情的な境界が尊重されず、明確な役割や限界がない状態を指します。こうした家庭環境では、親子や兄弟姉妹の間でお互いの境界が曖昧であったり、感情的、心理的な混乱が生じやすくなります。これは家族内のストレスや葛藤、さらには健康的な人間関係の構築に悪影響を与えることがあります。
バウンダリーがない家庭の特徴
過度な依存関係: 家族間でお互いに依存しすぎる関係が築かれていることがあります。たとえば、親が子どもに過度に介入する場合です。個人の自由や意思が十分に尊重されず、他者に過度に頼る傾向が強くなります。
感情的な融合: 家族内で個々の感情や意見が尊重されず、誰か一人の感情や意思が家族全体に影響を与えることがあります。例えば、親の感情が家族全員に反映され、家族全体がその感情に巻き込まれてしまうことが多いです。これにより、個人が自分の感情を持ちにくくなります。自分が何を感じているのか、自分が何を求めているのかが分かりにくくなることがあります。
プライバシーの欠如: 各メンバーの個人的な空間や時間が尊重されないことがあります。たとえば、家族間でお互いのプライベートな領域に無断で立ち入ることが日常的であったり、他者の持ち物や個人的な問題に干渉することが当たり前になっているケースです。例えば、子どものスマホを勝手に見てしまう、机の中にしまってあるものを勝手に見てしまうなどがあります。
境界が曖昧な役割: 家族内の役割や責任が明確でない場合、特定のメンバーが過度に責任を負わされることがあります。例えば、親が自分の問題を子どもに打ち明けて、子どもが親のカウンセラーのような役割を担ってしまう場合です。これにより、家族の中での役割が歪み、ストレスが生じます。
批判や干渉の多さ: 家族メンバーが互いに過剰に批判し合ったり、干渉し合うことで、誰もが自分の意見や行動を自由に表現することができなくなります。常に家族の他のメンバーの期待に応えようとするプレッシャーがかかることもあります。
バウンダリーがない家庭で育つ影響
バウンダリーのない家庭で育つと、子どもは大人になったときに他者との健全な距離感を保つのが難しくなることがあります。具体的には、以下のような影響が考えられます。
自己同一性の喪失: 自分自身と他者の境界が曖昧なため、自分が何を望んでいるのか、自分の感情や価値観が何かを理解しづらくなります。他者の期待や要求に合わせることが習慣化していることもあります。
依存的な対人関係: 他者との境界がうまく築けないため、親密な関係においても相手に過度に依存する傾向が強くなります。自分のニーズや限界を理解していないため、相手からも同様に限界を守ってもらうことが難しくなります。
対立回避の傾向: 家庭内で対立が過度に避けられていた場合、成長後も他者との衝突や違いを避けるために、自分の意見を表明できなくなることがあります。結果的に、他者に従いすぎて自己犠牲的な行動を取ってしまうことがあります。
感情の境界が不明確になる: 自分の感情と他者の感情を区別することが難しくなり、他者の感情に過度に同調したり、反応しすぎてしまうことがあります。これにより、過度に感情的な疲労やストレスを感じることがあります。
コントロールや支配の問題: バウンダリーがない環境で育つと、自己と他者の間のコントロールが過剰になることがあります。自分が他者をコントロールしようとするか、逆に他者に支配されやすくなる傾向が強くなります。
では、バウンダリーを作り直していくにはどうしたらいいのでしょうか。
また親は、子どものバウンダリーを作っていくためにはどうしたらいいのでしょうか。
これについては、「その後の不自由」(2010,上岡晴江・大嶋栄子)から、「女性依存症者の回復の目安」として書かれていることが参考になるかと思います。
なぜなら、女性依存症者たちの多くが、家族内でバウンダリーの問題を抱えており、そのことに苦しんできたからです。この女性たちの回復の道筋は、多くのバウンダリーの問題で苦しんでいる人たちにとって回復の目安になると思います。
1.自分の言葉でしゃべれるようになること
「夫が」「彼が」「誰かが」「お父さんが」「お母さんが」ではなく、「私が」としゃべれるようになること。
言葉は本当に大事です。日本語は主語を抜いても意味が分かる言葉ですが、主語が誰になっているのかは注意して聞かないといけないように感じています。「誰が」しているのか?ということは、非常に興味を持って聞かないといけないと思います。
2.自分の都合も優先できるようになること
相手の都合だけを優先するのではなく、交渉するということ。この「交渉」という言葉はいい言葉だと思います。「喧嘩」でもなく、「議論」でもなく、「無視」でもない。
自分の都合もそれなりに主張できるようになることが大切なのだと思います。
3.変化する自分の身体とつきあえるようになること
この本では特に女性について書かれているので、女性には生涯を通じて身体の変化があることが書かれています。思春期、生理、更年期といった年齢による変化、出産・授乳・育児による身体の変化があります。こうした身体の変化に気づきづらいことが、バウンダリーに問題のある女性には多いようです。
このことに気づいて、体の変化とうまくつきあえるようになることも大切なようです。
私は昨年の4月になぎさ心理相談室をオープンしましたが、自分の親との関係に問題を持っている30代から50代の女性の多いことにとても驚きました。親との関係は、自分が親になってもというよりも、自分が親になった時に気づくことが多いのかもしれません。
バウンダリーについても、たくさんのクライアントとの話の中で私が感じることが多く、ずっと考えてきました。読んだ皆さんの参考になれば嬉しいです。
参考文献:鴻巣麻里香(2024)わたしはわたし。あなたじゃない。リトルモア
上岡陽江・大嶋栄子(2010)その後の不自由 医学書院